新潟県新発田市の高橋建具製作所は、簾戸・格子戸など、和室・茶室建築の建具をオーダーで製作いたします。
㈲高橋建具製作所
■建具 Q&Adetail
目次へ戻る
□ 格子戸
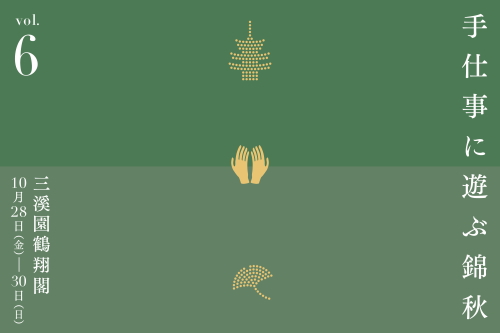
| Q、格子戸につかう材木は? A、玄関に使う時、雨風があたるので、水に強い木材の米ヒバ、青森ヒバ・木曽ヒノキを使います強度もあり、腐れにくい材料です。 ヒノキは色々な所でとれますが、良いものとしては、木曽のヒノキを使います。 青森ヒバは、殺菌効果があります。お寿司屋さんのまな板を頼まれるときは、青森ヒバを使います。 |
|
Q、格子戸の硝子はどう入れるのか? A、基本的に、格子戸は片面格子です。 硝子をとめる桟のホゾは、下を深くして、上を浅くする。そうやって、桟を外せるようにしてあります。 縦桟の本数は、基本的に奇数です。硝子の継ぎ目が真ん中にくるようにそうします。 両面格子の時は、上から硝子を落とします。 質問③(硝子が、ガタガタいわないようにするには・・・・) 4mmの硝子を入れるのに、4㎜のミゾをついても入らない。どうしても余裕が必要になります。 裏にシリコンかコーキングをうてば、ガタつきはとまりますが、それでは見栄えがわるいとなれば、上から溝の中に1本桟を入れて、遊びをとめます。厚みに関しては、どうしてもガタガタいいます。 両面格子にした場合は、ガタつきは結構とまります。 桟をくっついてしまうくらいに、きつく組みます。 きつく組むと、骨は曲がってきますから、それを利用して硝子のガタつきをとめます。 くでをきるときに、ちょっと強くきつめにして組みます。 普通に組むと、桟は広がりやすいので、きつめに組むのは有効かと思います。 |
|
Q、きつく組むという話がでましたが、その時の微調整はどうやってやりますか? A、機械でとっても、手でとっても、欠き込み部分を微妙にせまくします。 クデは、1つ1つではなくて、まとめて欠きます。まとめて墨をして、胴付鋸といううすい刃の鋸でとります。片方だけではなくて、両方で均等にとります。強さ確かめながら、やります。 機械はくできりです。家具屋さんなら、定規をつくって 横切りでよいかと。昇降盤でもいいです。 あれば、ラジアル。 ヒバなら、少し強めにしても入りますが、ナラやウォールナットのような硬い材料は、固く組むと組めなくなってしまう。材木によって加減します。 |
|
Q、格子戸が垢ぬけるコツは? A、隅々、穴をほって、桟がキチンとそこに入っているか? 取り合いがいかに、平らに納まっているか? 全体的に見れば、同じ形になっているけど、そういうところをきちんとすると垢ぬけると思います。  隅々を見ているところ |
|
Q、無垢の木は、汚れが気になりますが・・ A、木はどんな材料を使っても、手入れが大事です。 人間でも、手入れすることで、まるで変わってきますね。 亜麻仁油などの脂っけを与えること。 最初に納めるときと、なるべく近いうち、1年目くらいにもう1度に塗ったほうがいいですね。 |
|
A、背の高い格子戸は反りやすいですが、どうしたらいいですか? Q、一番は材木の見る目。100%絶対というのはないけど、だいたい見ればわかります。 それでも、背が高ければ高いほど、狂いやすい。あてのところは、木が硬い。まがっている。 いくら選んでいても、自然のものなので、どう変わるかわからない。 でも、自然のものだからと逃げないで、精一杯選ぶことが大事なことだと思います。 玄関は、片方だけ日があたるので、日当たりがよいところも気をつけなくてはいけないです。 そんなところは、素直な目の木がいいです。反るものという考えで、枠も作ってもらうと助かります。 背の高いものは、建具のすきまを、通常3mmのところを5mmくらいにしてもらうと、助かります。いい仕事だからと、すきまを少なくすると、後々お客さんが困ります。完成した時は、きれいだけど、すぐ、戸があたって使いづらくなります。 お客さんにも、無垢材は、反ることがあることを、一言伝えることも大事です。 また、上下の横桟が1本づつと、桟がとんでいるデザインは危険です。
|
