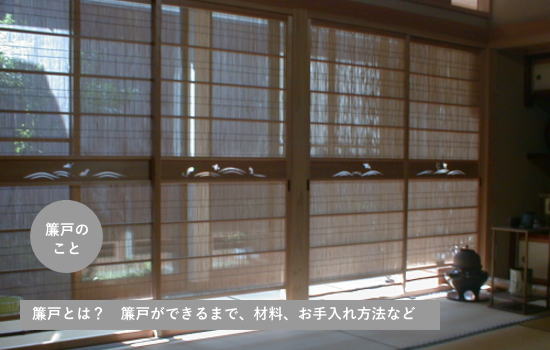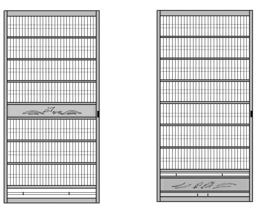新潟県新発田市の高橋建具製作所は、簾戸・格子戸など、和室・茶室建築の建具をオーダーで製作いたします。
㈲高橋建具製作所
■建具Q&Adetail
目次へ戻る
□ 建具に使う材木

|
Q、建具に使う材木の種類は 洋間のドアに使います。高級感があり固く、塗装の仕上がりも良いです。 重く狂いやすいのが難点です。 こげ茶色の木目の細かい木がタモ。北海道のタモです。 固くて色がおしゃれで、洋間にも和室にもあいます。 木痩せをおこしやすく、組むと口があいてくるのが難点です。 少し黄色っぽい木は、米ヒバです。木目のつまりもよく、狂いにくく、建具には使いやすい木です。 白っぽいのは、スプルスです。やわらかく建具を作るとき加工しやすい木です。 和室の造作材が白っぽい時(ヒノキなど)、合わせやすいです。 少し赤みのある木は、米松です。長く時間がたつと、もっと赤みが強くなりいい色になります。 難点はヤニです。必ず脱脂が必要。ただこの脂気が水に強く、玄関など外部の建具に向いています。 |
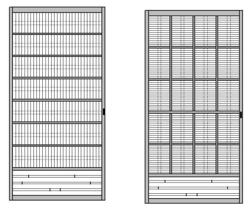 少しくすんだ黄色っぽい木は、青森ヒバです。現在とても少なく、貴重な材料。 水に強くお風呂に使います。 建具では、玄関に使い、千本格子にするとこの渋い色がいい感じで 落ち着いて高級感のある仕上がりになります。 白っぽいものは、ヒノキです。匂いでわかると思います。これは木曽ヒノキで国産材では最高級の材料です。 次の少し赤っぽい材料はサワラです。色がきれいで、昔は沢山流通していてよく使いました。 難点はヤニです。小口からヤニが出て敷居につき開閉がしにくく、 障子やガラスが入った建具ですと、そこにヤニが染みのようにつく事もあります。 次は、この3つ。実は全部杉です。 1つ目は、天杉と呼ばれる秋田杉の200年から300年の杉。 国有林がほとんどで現在伐採禁止になっているため、流通量が非常に少ない。やはり、杉の王様の風格があります。 2つ目は、新潟の杉です。 秋田杉に負けないほど目がつんでいて、200年くらいの杉です。今は、少し黒っぽいですが、時間がたつと淡いピンク色になり非常にきれいです。私は、地元の木のいうこともあり、この杉が一番好きです。 木目がちょうど1分(3mm)ほどで、遠目がきいて、とてもきれいです。 私のように木目好きなに人は、天杉ほど細かいものより、おすすめです。 3つ目は、150年ほどの秋田杉です。 今、沢山流通しているのがこの杉です。天然の杉もあるし、植林もあります。植林だって人が植えたというだけで、良い杉ももちろんあります。天然だから良いとか、植林だから劣るとかいうことはありません。実際見て、良いと思うものを選びます。 |
| Q、建具材とは? 建具に使う材木と、家をつくる材木は違います。丸太の使う場所も、丸太の挽きかた方も違います。 ただ、丸太のどこを何に使うのか?は、色々なケースがあり、その丸太の特徴や何に使うのかで多様です。 1本の丸太 (山にたっている木)があると、下から1番ころ、2番ころ、3番ころ・・と呼び 1番ころは、下から3尺(900mm)くらいを切ります。 ここは、建具の腰板にします。直径も大きく、力がかかっているので、複雑で面白い木目がでます。 芯をはずして、割っていきます。その時に番号をつけて同じ丸太からとった事がわかるようにします。 次の2番ころは、6尺くらいを切り、ここは天井板にする事が多いです。 建具材は3番ころ、4番ころ です。4mか、4m20cmに切ります。 昔は12尺 3m80cmでしたが、今は建具の背が高くなったので、4m20cmが多いです。 そこから上、家をつくる材料をとります。 ただ、最初にも言いましたが、大工さんがお寺をたてる時など、もっと下から5mで切る事もあります。お寺は3間とか、大きいので。だから、すべて同じではなくその丸太や、どの現場に使うのかで使い方が決まります。その木が一番引き立って、活きる方法がいいと思います。 |
|
Q、石(こく)とは? 1石=1尺x1尺x10尺 だいたい、1石で障子が15枚ほど出来ます。石x3.6=立米 です。 ただ、1石買ったらすべて使えるえわけではなく、3割はヒビや節で使えません。 |
|
Q、木取りとは?  私が親方に教わったのは、「木取りが終わると、だいたいの仕事は終わった」ということ。 この木取りで、建具の出来が決まると思います。 山にたっている木を見てわかるように、木は末広がりになっています。 だから、もちろん木目もまっすぐではなく、斜めになっています。 まっすぐの木目をとりたい時、どうすればよいか? 端からではなく、赤太と白太の境目から木取りします。ここが、一番木目がまっすぐで、きれいな部分です。 境目に狙いをつけて、その木目に応じて少し斜めにして割っていきます。 いい加減なようですが、これでまっすぐにいきます。 この良い部分を、4枚建具があったらその真ん中にくる框にもっていきます。一番目立つところ。 框とは、建具の縦の部分ですが、この長いところをとるのが一番大変なので、ここから取ります。 他の横桟は、短いので、節をよけたりしてとっていきます。 同じ丸太からとれた木を木取りすると、同じような色や木目の建具になります。 木取りをうまくすることで、安い木もとてもきれいな建具になります。そこが、楽しいところです。 |
|
Q、建具の部材名称は |
|
Q、木表と木裏について A、遠藤ケイさんが、「ちゃぐりん」という子供向けの雑誌に日本の手仕事を紹介するコーナーがあり 木表は、丸太の外の方で、木裏は中。小口を見ると、盛り上がっている方が木表です。
角の部材になって、小口を見ても、どちらが盛り上がっているかわからず、木表か木裏かわからなくなった時は、柾目の方よりも、木目の方を見るとわかりやすいです。 木目で目が浮いている方が木裏。目が沈んでいる方が、木表です。指でさわってみるとわかります。 |
| うちの会社では、建具を作る時、木表を全部、外側にもってきます。 遠藤さんもイラストで書いて下さっていますが、建具を1本の木と見ています。 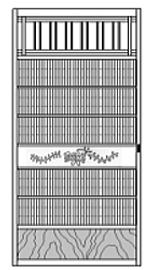 |
|
先ほど言いましたが、木裏は目が浮いているので、雑巾で拭いたとき、ささくれが出やすい。 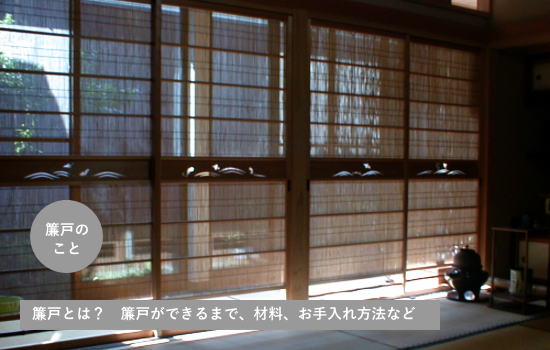 しかし、木表ということは、白太であることが多く赤太より柔らかく、固い赤太を外にもってくるところもあります。その会社のやり方で良くて、大事なのは外なら外で統一することだと思います。 節があったりして、当社でも木裏を外にもってくることもあります。木を無駄にしなかったり、それで、見た目の調和がとれれば良くて、何でもかんでも一律にというのは嫌だなと思います。 |
| Q、世界一軽い木で建具を作ってみたいのですが。 A、軽いということは、建具の開閉がしやすくてお年寄りには良いと思います。 作るときはホゾ穴が崩れやすいので組むというよりは、接着にしたり方法を変えた方が良いと思います。 |
| Q、家1軒分を同じ丸太でできますか? A、丸太1本、大きさにもよりますが1.8石から2.3石。 |
| Q、木取りの時、障子や格子戸の桟はどうやってとりますか? また、色が悪いところなどは、襖の中子にしたり、塗装をする建具にしたりして、なるべく捨てるところのないようにしています。
|